中日茶道比較
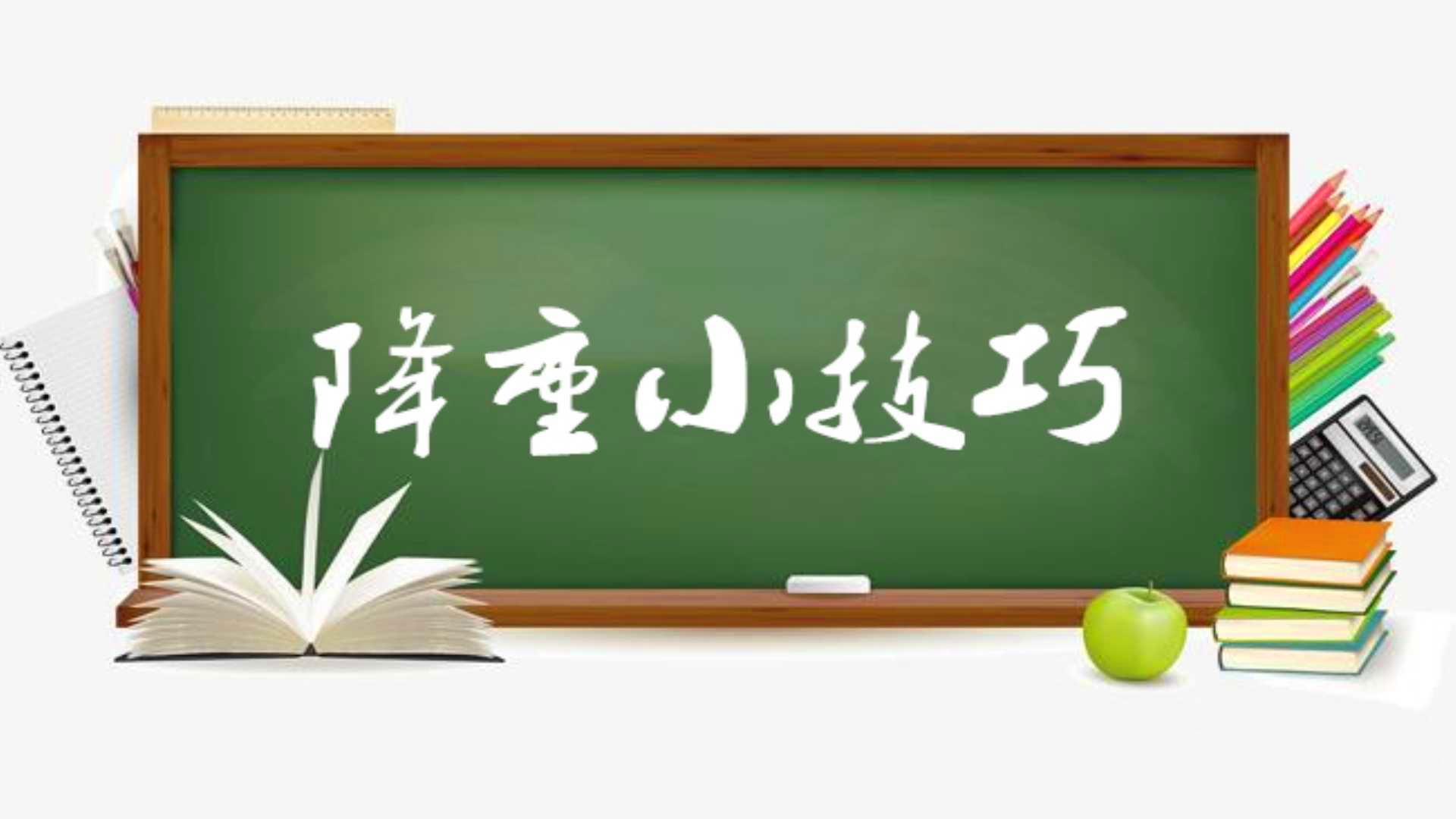
要旨
中國のお茶の歴史は三國時代から遡る。長い間中國の茶が世界に影響を與え続けている名作は唐時代の陸羽が書いた「茶経」である。その時からお茶を飲む活動は次第に王候貴族から一般の庶民へと広がった。宋時代と明時代を通して茶道は大きく変化し茶の葉の改良、茶器の発展、また茶道思想の完善を経て、今のようになった。
日本のお茶は平安時代に僧侶の最澄によりお茶の苗を持ち帰た。その後、村田珠光、千利休、豊臣秀吉などの名人が茶道に新しい製作法や禪の思想を導入し日本獨特な文化蕓術となった。
中日の茶道は自國の文化や歴史の影響により違う所がたくさんある。例えば茶の葉の種類、茶道の規則と過程また國民の性格と美意識などの方面で食い違う。
キーワード:茶道 中日文化 比較 茶道の活動 禪
摘要
中國的茶史可以上溯到三國時代。中國的茶在很長時間里對世界產生持久影響的是唐代陸羽寫的《茶經》。那時開始飲茶活動就逐漸從王公貴族普及到平民百姓。經過宋、明兩代茶道發生了很大變化。茶道從茶葉的改良、茶具的發展到茶道思想的完善逐漸成為今天的樣子。
日本的茶最初是在平安時代由和尚最澄從中國帶回日本的。之后,村田珠光、千利休、豐臣秀吉等人將茶道引入了新的制作方法以及禪宗思想使之成為日本特有的文化藝術。
中日茶道因本國歷史文化的不同在茶葉的種類、茶道規則以及國民性格、美意識等面有很大差異。
關鍵詞 茶道 中日文化 比較 茶道活動 禪
序論
茶道というと、みんな日本の茶道を頭の中に浮かぶだろう。中國ではいつも茶文化と言う。なぜ日本の場合は茶道と読むのか、それは道というのは日本の伝統的な文化の一つであり日本獨特な読み方だからである。みんなご存知のように日本のお茶は中國から伝われ、そして絶えず発展し今のようになった。この點から見ればと中國は日本の先生と言ってもいい。でも日本の茶道は中國のと同じものではなく中國と違う道を歩んでいた。なぜその違いが出てくるかそしてその違いがどこにあるか、私はそれについて詳しく解明したい。1. 中國の茶文化
1.1 茶道の定義
みんなご存知のように茶道は中國に源を発した。茶道の定義も時代の変化によって変わった。最初茶道の定義を決めたのは唐の時代にお茶を飲むことによって道を得ると言う意味だ。茶道の歴史は今まで発展しつつあり、茶道に対する定義もいろいろあった。ある學者は茶道を文化蕓能としてお茶を飲む活動と文化を完璧に結び、つまりお茶の中には道があり、お茶を飲むことによって道を得ると定義した。ある専門家は茶道を一種の室內の蕓能と呼ばれる。これらの定義を纏めると茶道とはお茶を飲む活動の形で精神的な感じと思想上の需要を満足すると言う意味である。ここでの茶道の活動は茶を植えることや茶の葉に対する研究ではなく、茶器、お湯やまたお茶を飲む場所に対する選択や飾りかたを含む活動である。
1.2 茶道の起源と発展
1.2.1 様々なお茶を飲む活動
中國はずっと昔からお茶を飲む習慣があった。「三國志」によると呉國の皇帝が宴會で酒を飲めない大臣にお茶を賜った。その時からお茶を飲む習慣が始まった。最初は生理上の需要を満足するだけで、茶を飲む環境や茶器、茶の葉の質に対する特別な要求がない。その後感覚器官によって茶を味わう活動が出てきた。つまり特定の環境の中でお茶をゆっくり飲み味覚、視覚などを利用してお茶を味わう。これによって美を求め、人生の秘密を探求するという精神的な享受に達する。
もう一つの活動はお茶を入れる蕓術(茶蕓)だ。つまりお茶を味わうことと違い、人の主體性によって茶器やお湯にぴったり合うものを選び、茶の色、味、形などの品質を充分に発揮する活動である。そして茶道の思想もの中に入れてきた。
1.2.2 茶道の起源と発展
茶道は中國の伝統文化の一つとしてその起源と発展はお茶を飲む文化の発展につれて生み出されたものだ。そして茶道の産生や形成また復興などは人間が自然や社會に対する認識、改造及び人類の活動と深い関係がある。
世界で第一回「茶道」という言葉が現れたのは唐の時代である。その時茶道は王候貴族の間に大いに行なわれてみんな茶がら付き飲む。それによって茶道が一定の格式を形成した。唐時代には政治、経済、文化がすごく発展し社會も安定していた。その條件の下で様々な茶道の流派が形成された。その中で一つは修行の形での茶道だ。この種類の茶道は一日中三回だけお茶を飲むと道を得ることができる。これは一般の人々にとっては難しいことだ。修行の茶道は古時代の詩人の陶淵明は都會から出て田舎に入って隠居の生活を送り、自分の希望や気持ちを花や森あるいは水の中に寄せるというような修行と同じ、僧侶が素樸な生活を送り現実中の悩みや不幸なこと、または不平等なことを回避するために茶道によって修行することである。一回だけお茶を飲むのは道を得られない。三回ずつ飲むと人間の肉體と心が徹底的に浄化され、神仙と人間を一體にする境界に達する。もう一つは茶蕓の形で行う茶道である。この種類の茶道については陸羽さんの書いた「茶経」がその代表作である。「茶経」は世界で初めてお茶のことを系統的に述べる本であり、中國の茶の歴史の中でも一番深い影響がある本である。茶蕓とは茶器や水などがお湯に対する影響もしくは茶の木の種類、栽培、加工、茶の葉の化學的な変化を研究することによってどのように質のいい茶を生産するかを考える過程である。そのうちにいろいろな道という精神的なものを得るのはこの種類の茶道の鍵だ。例えば、美味しいお湯を作るためにいろいろな調味料を適量に入れ、適當な火で煮る必要があるという例から國を治める時適材適當し、各階層の人間関係をうまく処理する必要があることが分かった。もう一つの例を挙げよう。「茶経」によるとお湯に適する水は一番いいのは山の水であり、次は海の水であり、最後は井の中の水である。この三つの水を見分けるために工夫をすることから物事に対する研究は表面に止まるのではなく、細かい所まで區別し物事をうまく把握する能力を育成する必要があることが分かった。つまり蕓能という茶道は人類が世界のあらゆる物に対する認識のレベルや、身につける程度を反映する。三番目は風雅の種類の茶道だ。これは前の二つと違い、のどの乾きを癒すために飲むのではなく、お湯や茶器などを選び、いいお茶を飲むのではなく、お茶を入れる過程を実演する形で現れる。そのうちに蕓術の趣が含まれ、鑑賞性や美術感に富む。この茶道の代表作は唐時代に出來上がった「氏を閉じてかぐことを閉じる」という本である。その本によると風雅の茶道とはお茶を飲む活動を通じて人々に精神文化の需要に実演の形での茶道を提供するということだ。つまり、物質的な享受と文化蕓術の享受を結び、茶を飲む活動に鑑賞性や文化蕓術性に富まらせることだ。これらの三つの種類の茶道の出現及び茶蕓に趣味を持つグループの形成がこれからの茶道の発展に重要な影響を與えた。
宋時代になると風雅の茶道と茶蕓の茶道が主流になり、以下の二つの特徴を持っている。第一、風雅の茶道は王候貴族から一般の庶民に普及した。その時國が繁栄し國內も安定している。貧しい人もお茶のことに注目を集めた。茶器も複雑から簡単に変わり庶民に受けられやすくなった。第二、茶蕓の形での茶道及び茶道の思想が普及した。具體的に言うと、お茶の精細さ質の良さを比較することによって、人間が世の中の物事に対する認識や理解及び把握の能力を反映した。このような茶道の思想は一般の庶民の中に普及するのではなく王候貴族の間にもよく伝わた。人間は物質の生活が満足している上精神文化を追求するようになった。これも平和の社會に積極的な役割を果たした。
明時代の初め頃朱権を代表とする茶道が人気がある。唐時代の団茶は葉の形の茶に変わった。茶道の思想も変化した。お茶を飲んでいるうちにお客さんが自分の意見を述べ複雑な社會から離れ心を清潔する。朱権の『茶の明細』という本は茶道の過程を詳しく紹介した。明時代の末期になると茶道思想は哲理の意味が弱くなり今のようにお茶を味わう要求と大體同じになった。
清の時代には茶の葉に対する需要が拡大し有名な茶もそれにつれていろいろ出てきた。陶器の現れは茶器に大きな変化をもたらした。その時お茶の産地を重視し茶蕓の活動も簡単になり茶を味わうようになった。改革開放後中國の生産力がずいぶん発展し物質の生活にゆとりがある。精神文化に対する需要が絶えず増えることは茶道活動の発展に條件を提供した。お茶を飲む活動はお茶を飲むことからお茶を味わうことまで茶蕓から茶道までこのように少しずつ浸入し、より多くの科學的な內容や精神文化の內容を含むようになった。二十世紀八十年代後、茶蕓の実演という形での茶道が盛んになった。そして実演の形も沢山ある。例えば宗教の形、風俗の形、古時代の茶道を倣う形などいろいろある。このような茶道は茶の自然科學と人文精神、文化蕓術を結び、時代に応じて新しい內容と形式を含む。2. 日本の茶道
2.1 茶道の文化定義
日本の茶道は中國から渡來したものであり、千年あまりの歴史を持つ。そして日本の社會文化と人文文化の発展につれて完善され、大和民族の獨特の環境の下で宗教、哲學、論理、美學、自然が一體になった。茶道が唱えられた「素樸、純粋、典雅」という精神は日本の茶文化を「道」の境界まで高めた。茶道は日本の伝統文化の代表として國民の生活の中でも不可欠なものになった。茶道の目的は渇きを癒すのではなく同じ茶の本質の優劣を鑑別するのではなく複雑なプログラムと儀式を通して情操を育成し靜寂の境界に達するのである。
2.2 日本のお茶の発展
中國の茶文化の歴史と比べると日本の茶道の歴史はそんなに長くなかった。歴史の資料によると、お茶が日本に初めて入ってきたのは平安時代であった。その時中國で留學していた僧侶の最澄によりお茶の苗を持ち帰ったそうである。奈良時代に上層の階級の間に喫茶の風習が始まった。その後、茶の木が近畿諸國をはじめ、各地に広く栽培された。鎌倉時代に栄西禪師をはじめ、沢山の禪僧が茶の製作方法と喫茶法を日本に伝えることによって茶道はどんどん進歩していた。喫茶の目的は鎌倉時代までは思想生活の伴侶として用いられたが(時には薬用)南北時代になると喫茶を遊戯的に用いた。つまり、闘茶として品種を飲み分ける競技の形で行なわれた。このような僧侶茶、武士茶は中國の茶文化に深い影響を受けた。これは日本茶道が生まれる前の歴史だ。
本當の意味を持つ茶道は十五世紀の末ごろ村田珠光氏により創立された。村田珠光氏はお茶を飲む行為に思想を入れる初めての人であり、日本茶道の祖先と言ってもよい。その後武野紹鴎によりさらに推し広めていった。日本の茶道の精神も「茶と禪が一體になる」ような境地になった。千利休はもっと具體的かつ系統的な規則を定め茶道を庶民化にさせた。また茶會の種類、茶器の種類や茶室、庭の飾り方なども決めた。日本の茶道は今でも絶えず発展しているが茶道の基本的なものを決めたのはやはり千利休だ。でも茶道の大成については織田信長、豊臣秀吉の成果を無視してはならない。彼らは茶道を政治的に利用したが茶道に精神的な慰安を求めた。千利休は「謹敬清寂」を「和敬清寂」に変化させた。江戸時代に千利休の子孫と弟子が茶道を継続し「家元制度」注①を作り別の流派が現れた。千家流派は表千家、裏千家と武者小路千家三つの大きな流派になった。この時期は日本茶道の輝かしい時期であり、日本民族の特徴を持っている。また抹茶道、煎茶道も形成された。明治維新以來茶道に深刻な変化が現れ文化的な意味が強くなった。そして時代に応じて自國の特徴を持っていて今のようになった。
2.3 中國の茶文化が日本の茶道の発展に対する影響
日本の茶道の形成と発展が中國の茶文化と深い関係がある。まずお茶を飲む風俗は最初に日本に入ってきたのは平安時代のことだった。日本の天臺宗の創始者である最澄は中國の仏教の経典と茶の木を持って帰った。そして栄西は鎌倉時代にもう一度中國の茶を持ち帰り、「喫茶養生記」という書物を作った。その本は日本の茶道の歴史的な転機と言ってもよい。また栄西は茶に対する栽培、茶の葉の摘む方法、飲む方法を詳しく紹介した。それと同時に中國から寺のお茶の飲み方を導入しお茶を飲む禮儀を定めた。例えば団茶、抹茶、闘茶などは全部中國から伝わられたものだ。ほかには毎年の春と秋、奈良で行なわれた茶會特に唐式の茶會は日本の茶道の源である。それは中國の唐と宋時代の茶會によく似、茶を飲む庭の飾り方や點茶の儀式及び闘茶遊戯などが含まれる。
これだけではなく栄西は平安時代の終わり頃中國の宋に學び日本に禪宗を開いた。禪文化は日本の伝統文化の中で重要な內容であり、禪宗の導入と伝播につれて形成された。日本の茶道から中國の仏教思想の跡もよく見られる。日本の茶道の和敬清寂という精神は仏教の教義の中にはっきり書かれてある。「茶禪一味」注②という茶禮もそれと同時に導入され、室町時代になると五山僧の間に次第に定著して行った。
本文收集整理于網絡,如有侵權請聯系客服刪除!



